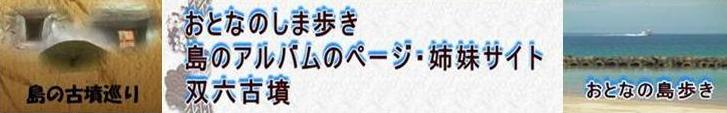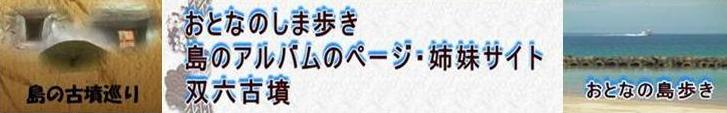| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
双六古墳
6世紀中ごろの築造で、長崎県最大の前方
後円墳。
全長91メートル、前方部の高さ5メートル、
後円部の高さ10.6メートル。
入口が南西に開口する横穴式石室で、
全室右側壁には船の線刻画がある。
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
弥生時代の末期には、倭国の内紛を経て、各諸国の統合が進んだ。
その中核を担ったのが大和政権であった。
大和政権は、地方支配を願望する首長らの要求を受け入れた。
それと同時に、この世とあの世との世界を相似形に考えた中国の神仙思想を取り入れて巨大な
前方後円墳が各地で出来あがった。
前方部から後円部は、葬送儀礼のために人が古墳へと登って行く道であり、そこで粛々と葬送儀礼が
執行され、緩やかな道を通って、時の権力者たちが死者を弔問したのである。
このように前方後円墳は、今までの墳墓とは全く異なる大和政権の支配下にある証しでもあった。
400年にわたって、中央、地方を問わず競って作り続けた前方後円墳は、646年大化改新で薄葬令が
出されて墓は簡素化することとなった。 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|